
横浜DeNAベイスターズ ビジネススクールで展開する ”世界最先端”の取り組みと「全員が真に一体となって選手と向き合うチーム」に向けた人材育成
育成そして補強へと繋がるITテクノロジーの活用
「国際戦略・海外球団との連携」では主にMLBチームとの提携についての内容に。
ベイスターズはアリゾナ・ダイヤモンドバックス(以下、Dbacks)と19年に業務提携を締結し、以降チーム間の情報交換や人材交流等を20年春まで行ってきた。
講義では複数球団の中からDbacksを選定したプロセスなどを紹介した。人材交流は昨年までコロナ禍で中断していたが、今年より順次再開する予定である。
そして壁谷さんパート最後のテーマは「最新テクノロジーの導入、R&Dチーム立ち上げ」。
ベイスターズでは前述のトラックマンなど、12年から16年の間で最新テクノロジーを導入し続け、球界でもトップクラスのIT整備を行っている。
17年からはR&D(Research & Development)グループが立ち上がり、育成に繋がる取り組みを強化してきた。
ここで取り組んできていることはパフォーマンスを可視化させることで、その向上や調子のバロメーターとして活用することである。
打撃や守備にも活用されているが、ここでは投手陣における事例を紹介する。
Dbacksの人材交流でも現場のコーチから教わったものの一つである「ピッチデザイン」を実践した。ピッチデザインとは、選⼿・コーチ・AT(アスレティックトレーナー)・R&Dグループの4者で理想的な投球やその実現可能性を前もって議論し、その選手のスタイルを確立するものである。

ここでの成功事例が昨シーズン自己最多の11勝・防御率2.77をマークした大貫晋一投手。
プロ2年目の20年、初の2桁勝利である10勝・防御率2.53でブレイクを果たし、現在も先発ローテーションの一角を担うまでに力を伸ばしていった。
「大貫選手はすごく興味を持っていて、『こういったスライダーを投げたいんです』というところから始まり、それを投手コーチやアナリストらと共同で試行錯誤しながら磨いていきました」(壁谷さん)
また、補強面でもデータと駐⽶スカウトの⽬利き・感覚を組み合わせることでより確度の⾼い補強に繋げてきた。
R&Dグループが発足した17年以降、獲得した外国人選手はジョー・ウィーランド、スペンサー・パットン投手、ネフタリ・ソト内野手など、投打の助っ人として数年に亘り活躍している。
講義で紹介したのはタイラー・オースティン選手の例。オースティン選手は20年に入団すると初年度は65試合の出場ながら打率.286・20本塁打・56打点でOPS.969の成績、21年は107試合出場で、打率.303に加えいずれもチームトップの28本塁打・74打点でOPSも1.006をマークした。
獲得に至った決め手の1つとして、打球速度に着目。19年にMLBで89試合に出場したオースティン選手は、打球速度が全体で28位とトップクラスの数値を記録している。
これらのデータ、そして現地スカウトの見解とすり合わせをしながら選手を獲得している。
オースティン選手は、昨年10月に右肘内側側副靭帯修復手術を受けリハビリ中。復帰後の打棒が期待されている。
次ページ:ベイスターズの行う人材開発の歴史や取り組み


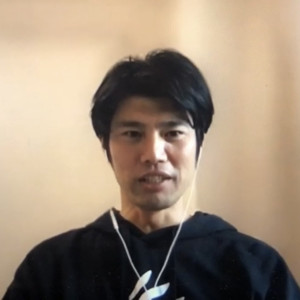


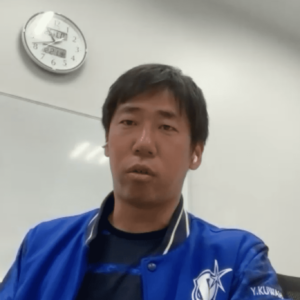
(4009)--300x300.jpg)
