
横浜DeNAベイスターズ 日本一を成し遂げた”組織づくり”とは?「自己進化型組織」でつくり上げるチーム改革の方程式
昨季26年ぶりの日本シリーズ制覇を果たした横浜DeNAベイスターズ。ポストシーズンを勝ち上がり、横浜の街に大きな希望と歓喜をもたらした。
要因として、約5年の歳月をかけて行ってきた”組織づくり”が挙げられる。1月某日、ベイスターズが取り組んできた「自己進化型組織」に関するスペシャルセミナーが開催された。
今回はそのプログラムの一部を2編にわたってお送りする。
(写真 / 文:白石怜平)
日本一は「狙ってつくった」結果
今回は、球団が採用している「自己進化型組織」の取り組みを体験できる特別セミナーとして開催された。
この取り組みはスポーツチーム以外の組織にも通ずるものがあることから、より広く知ってもらうことを目的として開催が実現した。
初回の講義では「自己進化型組織」を球団に導入し、変化の礎をつくった川尻隆・組織改革アドバイザー(現・チーム統括本部 育成部 パフォーマンスコーディネーター 兼 S&Cグループ グループリーダー)が登壇。
川尻氏は5年間の軌跡と共に、従来の常識を超えた組織づくりにおける具体的なポイントなどを明かしてくれた。

まず、昨年の結果については「ペナントレースが終わってから、日本シリーズに入るまでの流れ。これは偶然起きたことではなくて、”狙ってつくった”ものです。なので、我々にとっては日本一という結果に驚きはないんです」と語った。
球団が自己進化型組織を導入したのは20年の夏頃。
前年にはあるべき姿や姿勢などを記した「ビジョンマップ」の策定や、人材開発の組織を立ち上げるなど、改革を進めていた時期でもあった。
横浜DeNAベイスターズが誕生して以降、力を入れ続けている組織づくりをさらに強化するため、必要な考えだとして自己進化型組織を採用した。
「我々が30年先・40年先にも組織として生き残っていくために必要なものとして導入したのが最初です」
肝になる”自責”の考え
川尻氏は一つワークを提示。それぞれの所属先で起きている課題・問題を書き出しテーブルの中で共有し合った。これを踏まえ、以下のように解説した。
「目の前に起こる出来事を”現象”と呼びます。これは、常に個人×環境の組み合わせによってできているものです」
もうひとつのワークとして、各々挙げた現象が「個人」・「環境」のどちらに該当するものなのかを考える時間を設けた。ワーク後、川尻氏は説明をこう続ける。
「各現象で誰を対象にしていますか?自分それとも他者ですか?ほとんどの場合、他者になっていることが多いと思います。『部下が〜』とか、『上司が〜』などというように。しかし、捉え方を変えるとみなさんも他の人にとっての『誰か』になっていませんか?
皆さんにとって目の前で起きている現象ですが、このときの”個”って他者ではなく自分なんです。でも、多くの場合我々は問題である現象の原因を他者であったり環境だと思ってしまっている。
要するに、多くの人は結局誰かのせいにしているんです。今の皆さんも含めて。でも、誰かのせいになっている限り変化が起きることはないんです」

現象は「個」と「環境」の掛け合わせであると説いた
では変化をどのようにして起こすのか。組織を構築するにおいて一つ大切な考えを川尻氏が述べた。
「現状起きていることを変えるために、自分がどうやったらそれを実現できるか。そんなマインドをつくる。自分の責任であるということで、『自責になりましょう』というのが大切な考えになります」
この”自責”というのが、自己進化型組織において重要なキーワードのひとつになっている。さらに深掘りするように説明を続けた。
「今まで良い組織を作りたいときは、環境に対するアプローチは多く行われていることなんです。でも、個に対するアプローチって行われていない。良い組織が生まれる・チームが強くなるという現象を作り出すには、この両輪(個と環境)が必要になります。
つまり両方へのアプローチを行うわけなので、片輪走行ではいけない。しっかり環境と個の両輪を動かしていきましょうと。それができて初めて本当の意味での組織を構築できるんです」

「勝ち切る覚悟」を生んだ”一人の勇気”
”自責”の考え方が浸透し、結果として現れたエピソードがあった。川尻氏は昨年8月下旬に発表した終盤戦のスローガン「勝ち切る覚悟」ができた時のことを挙げた。
このスローガンは一人の”勇気”から生まれたものだったという。
「ビジネス側の一人が『我々がチームを勝たせないといけない』と声を発したんです。今まではビジネスは稼ぐ・チームは勝つというようにそれぞれ明確な役割を持って活動していました。
そこから、ビジネス側がチームの勝利に対して自責になったんです。声を上げた本人は内心戸惑いがあったみたいですが、”一度口に出してみよう”ということで、勇気を出して話してくれたんです」

スローガンについてはビジネス側とチーム側が一つになって考案し、チーム側の担当者がしっかりと選手たちとコミュニケーションを重ねた。最終的にはキャプテンの牧秀悟が「勝ち切る覚悟」に決めて完成した。
「組織は自然とまとまるんです。与えられたものではなくて、自分たちでつくったものだから。ビジネス側とチーム側が一つになった。結果、それが力になって日本一に繋がったんです」

組織を変えるには一人の勇気がきっかけになったのはこれだけではないと、川尻氏は語った。もうひとつエピソードを紹介した。
「一日の始まりと終わりに選手や首脳陣・スタッフが必ず全員集まって、メディテーション(瞑想)とチャッティングをしています。始めたのは昨年5月だったのですが、それをチームの一軍運営のトップである吉川が提案したんです」
当初は違和感も一部で持たれたという取り組みだったが、導入してから継続することでそれがルーティーンへとなった。シーズンを終えての秋季練習や新人合同自主トレでも自然に行われている。
「これも勇気を持った一歩からスタートした施策です。8月頃からは違和感を持つ声もなくなっていましたし、今はそれが”当たり前に”なっています。
ここで伝えたいのは、組織の大きな変化って誰かの勇気ある一歩からスタートします。その一歩を支えるのが組織なんです。
我々は5年の歳月をかけて継続してきたことによって、今ここにいますし、日本一になることができた。なのでこの結果は必然だと全員が思っています」
自己進化型組織を実現する方程式とは?
続いては”進化”について紐解いていく。川尻氏は自己進化型における考え方のベースとして、「多様性」×「選択圧」が高く保たれていることだと説いた。
ここでの多様性とは、年齢や性別という意味ではなく「異なる価値観や考え方がより多く存在すること」である。また、選択圧とは「進化しなければいけない状態を生む」こと。
この二つを高めていくことで、組織が進化する方向へ自然に向かっていくという考えに基づいている。
「自己進化型組織の肝というのは、いかに多様な人たちを1つの方向性に向けられるかです。多くの場合は、それを認識してても方向性の統一を図れなくなってしまいがちです」
ここで川尻氏は、多様な価値観を一つの方向性に導くために行っていることを述べた。
「意思決定の仕組みにあります。多様なインプットから一つの意思決定でどう作っていくかです。必ず一人で行わなければいけないのがポイントです」

さらにカギとなることについては「みんなの意見をまとめない」ことだと説いた。その根拠を交えながら以下のように続けた。
「全員の意見をまとめたり取り入れようとしてしまうと、60点・70点のものしかできないです。でも意思決定者を一人に絞ることで、その人の考える100点が担保される。
さらに多様な意見が出てくることで、新たな発見が加わるので意思決定者が自分を超える。要するにチームとして自分を超えていく仕組みになります。
そして、意思決定者以外のメンバーも自分の価値観に沿った意見をちゃんと出して参加しているので、前向きな納得を持って物事を進めることができるんです」
この他にも自己進化型組織の構築について様々な考えを伝えた川尻氏。ベイスターズでは5年近くの時間をかけて浸透させ、”組織で勝つ”ことを実現させた。
「日本のトップスポーツとも言えるプロ野球の一球団が、このような取り組みで日本一という結果を出したというのは、社会的なインパクトがすごくあると思います。
我々は自分たちの組織だけではなく、スポーツ界さらには日本をより良くできる可能性があることを感じているのです」
今季は「横浜奪首」のスローガンを掲げたベイスターズ。一つになった組織で戦い、昨季以上の結果を出そうとしている。
【関連記事】
横浜DeNAベイスターズ 26年ぶり日本一の裏側「自己進化型組織」の浸透で「全員が勝利を自分ごと化」へ
横浜DeNAベイスターズ 「第5期 横浜スポーツビジネススクール」開講!プロ野球の移り変わりから見る企業としての在り方と成長を支える人材開発の思想
横浜DeNAベイスターズ パネルディスカッションで共有された”横浜に愛される”までのプロセス〜第3期横浜スポーツビジネススクール


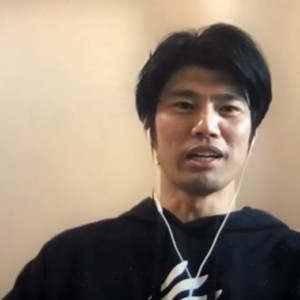



-300x300.jpg)
