
甲子園夢プロジェクト 5年間の軌跡① 〜硬式野球を通じた絆の輪は地域そして世代を超え全国へ〜
特別支援学校に通う、知的障がいのある生徒たちが硬式野球でプレーする「甲子園夢プロジェクト」。21年に発足し5年目を迎えた同プロジェクトは、年々進化と発展を遂げている。
発足から現在そして未来に向けての道のりを、玉川大学准教授でプロジェクト2代目の代表を務めている阿部隆行さんに伺った。※全2回のうち1回目
(取材 / 文:白石怜平、表紙写真:甲子園夢プロジェクト)
特別支援学校生が甲子園を目指すプロジェクト
「甲子園夢プロジェクト」とは、特別支援学校に通う生徒たちが“甲子園に出場”したいという夢を支援するもの。
知的障がいのある生徒たちが硬式野球に挑戦し、各都道府県の地方大会に出場する選手たちを輩出している。
同プロジェクトは東京都立青鳥特別支援学校で主任教諭を務める久保田浩司さんが発起人となり誕生した。
久保田さんはその前に赴任していた特別支援学校でソフトボール部を設立しており、20年ほど前から生徒たちの心身と技術を高めていた。健常者チームとの試合でも勝つなど、レベルも上がっていった中で次のステップを描いていたという。
「おそらく軟式野球も考えたのかもしれませんが、久保田先生は元々高校野球の指導者として『甲子園に行きたい!』という想いを持っていました。
そんな中で、『この子たちだったら野球をやっても大丈夫』と感じるまでソフトボール部のレベルも上がっていたので、自身の夢と合わさって硬式野球への挑戦を決めたのだと思います」
そして21年3月、甲子園夢プロジェクト(以降、夢プロ)として正式に発足。当時、すでに大学教員を務めていた阿部さんは発足を知るとすぐに久保田さんへ“売り込んだ”という。
「私も元々はキャリアのスタートは特別支援学校でした。そこから高校で野球部の監督や部長を経験した後に大学教員になったのですが、久保田先生が(プロジェクト発足を)発表したのを見て、すぐ連絡しました」

阿部さんは高校球児として甲子園の舞台に進んだ身。自らは怪我によりスタンドから応援する立場であったが、夢の舞台を肌で感じている。
加えて特別支援学校での教員、そして高校野球の指導者と条件を全て満たしていた。
「これ以上適任者はいないだろうと思って(笑)、自分から『お手伝いしたいです』とお願いしに行きました」
2年目に早くも地方大会出場者を輩出
発足した初年度は、11名の特別支援学校生が集まった。新聞記事に掲載された案内と連絡先を見た学生たちが自ら門を叩いた。
愛知県や京都府からも来るなど、早くもその反響は全国へと広がる気配を見せていた。初練習となった新木場の練習場では、元プロ野球選手も駆けつけた。
「久保田先生とのつながりで、元ロッテの荻野忠寛さんが打撃投手として生徒たちに投げてくださったんです。みんな嬉しそうに全力でバットを振っていて。ここが原点になりました」
ただ、継続して開催するにはハードルが立ちはだかった。硬式球やバットを揃えるには相応の費用がかかると共に、硬式球で練習できる場所も限られるため確保も容易では無い。
そのため、久保田さんらは伝手をたどって高校の硬式野球部を回った。そこで合同練習を実施するなど、この機会を楽しみに遠方からも集まった生徒たちが野球に打ち込めるよう尽力を重ねていた。
月1回の練習会開催を1年以上継続し、2年目に一つ大きな成果が表れた。愛知から参加していた林龍之介選手(豊川特別支援)が県大会に出場した。甲子園夢プロジェクトから地方大会に出場した選手を早くも輩出したのだった。
「彼は経験者で地方大会に参加できる!という確信を持って来たわけではなく、純粋に硬式野球に挑戦したくて夢プロに参加してくれました。
久保田先生も真摯に向き合って参加できる方法を調べたり、後は愛知に行って学校と交渉したり、県の高野連にお願いに行ったりして参加が実現しました」
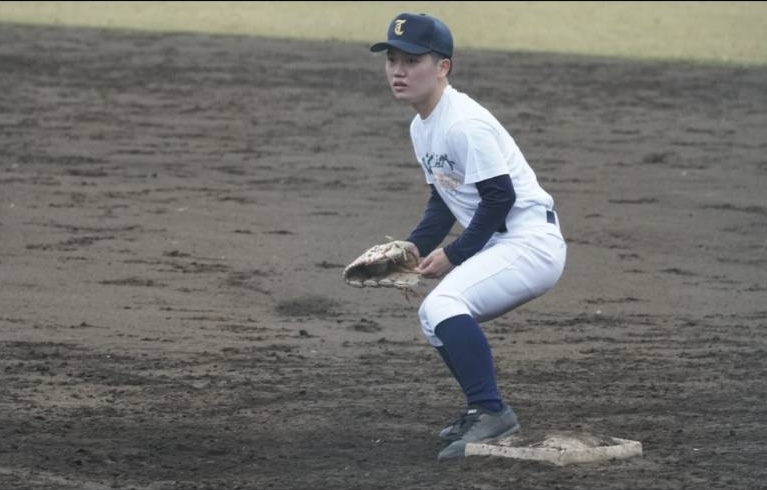
そして、林選手そして一番近くにいた人たちの熱い想いが夢を現実へと引き寄せた。
「林くん本人もですし、ご両親の熱意が学校を動かしました。高野連としては学校が許可して、かつ連合チームとして手続きを踏んでくれれば出場は可能という見解だったので、豊川特別支援として硬式野球部が結成されました。
ただ、部員は1名なので5校の連合チームの一員として彼はメンバー入りすることができました」
22年7月15日に行われた一宮西高との試合で六回裏に代打での出場を果たし、歴史に新たな1ページを刻んだ。
阿部さんは当時夢プロでは選手たちのトレーニングを技術指導を担当していた。林選手の姿勢をこのように振り返った。
「月1回の練習には愛知から欠かさず参加していましたし、ウェイトなどの重い筋トレは数日置きにやって腹筋は毎日やって大丈夫だよって伝えたら、(腹筋を)欠かさず続けてくれました。野球をやれて本当に嬉しいんだなっていうのが姿勢で伝わってきましたね」
今も続く全国制覇も果たした名門校との縁
県大会出場という、一つ大きな目標を達成した夢プロはさらに拡大を見せる。林選手のニュースが全国的に報道された反響もあってか、22年度の参加者は40人となった。
中には北海道から新たに参加するなど、その輪が全国へと広がりを見せた。23年には深い絆がスタートする出会いがあった。
「あの年に最も大きかったのは、慶應義塾高校さんとの交流が始まったことです」
この年に全国制覇を果たすことになる慶應高とは合流練習を年2回ほど行うようになり、それは現在も続いている。当時はコロナ禍だったため、部員同士でオンラインでの交流も行っていた。
そして慶応高との関わりをきっかけに、高校との縁も次第に広がっていった。
「『慶應さんでやっているなら、ぜひ我々も』という形で、一緒に練習してくださる学校さんが増えてきました。久保田先生の他にもスタッフがいて、そのお知り合いの学校さんと繋がったりもありましたね」
迎えた同年の夏、夢プロとしてまた一つ新たなステップを刻んだ。
「青鳥特別支援学校が連合チームとして、西東京の地方大会に出場できたんです。東京での出場実績を新たにつくれたこともそうですし、何より久保田先生の学校で出ることができたのでとても意義あることでした」

全国各地の地方大会に出場するための確かな足がかりをつくった。しかし、その一方で夢プロジェクトとしては一つの節目を迎えなければならなかった。
「青鳥特別支援学校が高野連に登録されたことで、久保田先生が夢プロを退かないといけない状況になったんです」
久保田さんは翌年以降も同校の野球部として指揮を執る必要があり、他の団体と兼務しながらは活動できない。そのため、甲子園夢プロジェクトの運営体制の再整備が急務となった。
そこで後任の代表として白羽の矢が立ったのが阿部さんだった。ただ、久保田さんが創り上げたこのプロジェクトをそのまま引き継ぐのにはプレッシャーと不安が交差していたという。
「久保田先生のようにはできる自信はなかったので、正直迷いました。
ただ、私としても、プロジェクトとして年々成長して40名も『これから自分たちもがんばるぞ!』とモチベーションがすごく出て盛り上がっていたのを感じていましたし、何より親御さんたちですよね。
『硬式野球ができる環境に出会えたので何でもしてあげたい!』であったり、『できないと思っていた硬式野球に打ち込んでいるその姿を見ているだけで嬉しい』と言ってくれていた親御さんに“解散します”なんて言えないなと。
なので、『自分ができる範囲ですがやります』と7月に受けることにしました」
そして、夏の大会後にさらに夢プロへの希望者が増え、50人にまで拡大し3年目を終えた。

阿部代表が実現した拠点の拡大と多世代交流
阿部さんは23年夏に代表となってから、ある構想を抱いていた。
「活動そのものを全国展開したい想いがあって、交流する学校さんを関東から広げていこうと動きました。というのも、全国から東京に月1で来てもらうのは申し訳ないなと。なので、参加してくれる生徒の地元で開催できるような環境づくりを今も構築しています」
まずはスタッフ間の人脈を活かしながら、大阪での定期開催を実現した。加えて阿部さんは、さらに一つ自身のアイデアを交えていった。
「あとは他世代間の交流も強く意識しました。高校の男子の野球部だけではなく硬式の女子野球部や大学生・社会人のクラブチームなど様々な世代と関われるようにしていきました」
現在自身が准教授を務める玉川大学で受け持っているゼミ生が練習会に参加したり滋賀大とも合同練習を行うなど、地域・世代問わずその絆を広げていった。

昨年12月にはついにNPBともコラボするまでに発展し、「読売ジャイアンツ×甲子園夢プロジェクト コラボ練習会」を読売ジャイアンツ球場で開催した。
「久保田先生が代表を務めていた時代からジャイアンツアカデミーと交流があって、『夢プロさんと何かやりたいですね』というお話をいただいていました。
それで、昨年巨人が球団創設90周年でしたので、それを記念した特別企画として開催していただきました」
本練習会ではアカデミーコーチや女子チーム、さらには現役のコーチや選手からも指導を受ける特別な時間に。
現在も練習で一軍選手も活用する球場を舞台に、憧れのプロ野球チームや選手たちと交流するため、全国から27人の学生が集まった。
このように阿部さんが代表として自身の構想を形にした24年だが、実は今年にかけてまた一つ野球界に新たな風を吹かせていた。
(つづく)
【関連記事】
甲子園夢プロジェクトが初のBaseball5に挑戦!ジャンク5が描く“『ベースボール型スポーツで『共生社会』を実現する”大きな歩みに
Baseball5 ジャンク5が「ジャンクサマーカップ」開催 唯一無二の環境が生み出す、“真剣さ”と“楽しさ”の共存空間







